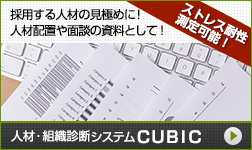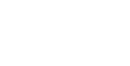トップページ ≫ 団体案内(概要) ≫ ヒストリーof社労士 ≫ vol2. 関連団体の動き
ヒストリーof社労士
» vol2. 関連団体の動き
さて、これまでもまたこれからも出てくる言葉だが「関係(あるいは関連)団体」というのがある。これはどういう意味を持つのか少し説明してみたい。社労士法制定以前の労務管理士たちの「管理士」のサムライ名称は、前述のとおり私的称号である。
30年代後半、労務管理士などの称号を与える、いわゆる労務コンサルタントに類する専門家育成を目的とした団体は、全国団体、地域団体を合わせて約30になんなんとした。また、社会保険士の称号を与える団体は厚生省関係の日本社会保険士会が唯一の団体であった。
30近い労務管理士関係団体の中で、前述の社団法人「日本労務管理士協会」が唯一の所管官庁許可の公益法人であり、他の団体はすべて任意団体である。つまり、身分法制度に向けて各任意団体は、2つの公益法人に吸収されるか合併されるか淘汰されていく。
つまり、関係団体というのはこの時点ではこれらの諸団体を指したものである。
さて、戦後の経済混乱と、労働基準法などの新法施行に伴い、中小企業を対象として自然発生的に生まれたのが労働事務代行業であることは述べた。
30年代、わが国経済が高度成長期に入り、企業の先行投資と業績拡大は人手不足に拍車をかけた。中卒労働者を金の卵と呼んだのもこの時期である。中小企業の体質改善や近代化が叫ばれ、中小企業経営者はいや応なしに労働管理の改善に取り組まざるを得なくなった。
当時の総理府の統計により、わが国の企業規模をみると、製造業での一事業所当たりの平均従業員数はわずか14人、商業・卸売業で7人、小売業にいたっては1人というのが実態だった。このことは、わが国の企業規模はいかに零細企業が多いかを物語っている。
大手企業では労務担当重役をはじめ労務専門分野を整備し、出先の工場や営業所にも専任のスタッフを配して万全の態勢を整えている。しかし、多くの中小零細企業では、相当の規模でない限り、労務担当者を置く余裕はない。かといって法定の各種保険、労基法関係の諸手続きや届出などを人がいないからできないでは済まされない。高度成長期を迎え中小企業の体質を近代化しようというかけ声のなかで、専門職としての事務代行業が育っていったのである。
ところが、この事務代行業者のほとんどが行政書士法に違反していた。行政書士法第1条には「他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とある。つまり、行政書士の資格をもった人以外の人は“報酬を受けて業として”はならないということだ。
事務代行業の人たちの中でも、役所のOBや心ある人たちは、事務代行業を目指す場合必ず行政書士会に入会し、行政書士という身分法の資格に基づいて業務を行った。一方労務管理士の養成団体の講習を受け、団体がその修了者に与える任意の士(サムライ)の資格で事務代行業に入った人たちは明らかに行政書士法に抵触するし、当然、各地の行政書士会から摘発されたり、それを機に行政書士会に入会した労務管理士が多くいた。
社労士法制定化に当たり、日本行政書士会連合会(略称日行連)が法施行に伴う特例措置や移行基準が、日本労務管理士協会や日本社会保険士会などの団体に有利になることを警戒し、また、行政書士には無条件で資格を付与すべきだと主張したのも、自分たちの職域が社労士法制定によって侵されるという強い不安から出た当然の動きでもあった。
特に行政書士が行政に対して大きな不信を持ったのは、移行基準策定に際し、任意資格で業を行っていた労務管理士、社会保険士などに対する「開業歴証明」を労基署、職安、社会保険事務所などから出すといううわさが広まったときだった。
行政書士法違反で摘発しなければならない対象を、国の出先機関が”優遇”することになりかねない措置だけに、この実現を阻止するために日行連が全国的に結集して対抗しようとしたのも当然だった。さらに、法施行後1年間は、法で禁止される類似名称が経過措置によって使用できることも、行政書士法本来の建前からいっておかしいという議論が起こったのも当然であった。
こうした正論を引き提げて日行連傘下の各地方行政書士会は、社労士法関連の労働・社会保険諸法令に習熟し、無条件資格付与の裏打ちをしようという動きが高まり、実務研修会が自主的に開かれ、行政もこれらの研修・講習会を積極的に支援した。また、一定の講習・研修を終えた地方会では、行政書士会とは別格の社会保険労務士会の結成をいち早く済ませてしまうところも出るなど、社労士有資格者という自負心から行政書士を中心とする団体の結成は全国に広がっていく。
もうひとつの関連団体は日本税理士会連合会(略称日税連)である。日税連も新法には並なみならぬ関心を示した。税理士業務に付随して行われる賃金計算、社会保険・労働保険料の算定や計算などの業務が社労士法に抵触することから、日税連は税理士に対する特別措置を求める方向で運動を展開していった。
税法と社労士法との関連は、㈰所得税の非課税に関する法令(健康保険法第69条など26項目)、㈪所得税の課税上の特例に関するもの、㈫所得税法第29条において給与とみなす年金(国民年金法など8法令)、㈬所得控除を適用される社会保険料(健康保険法など14法令)、㈭小規模企業救済法など、㈮預貯金の範囲など7法令——など、きわめて密接なものがある。
日税連傘下の税理士は当時約2万人。そのうち実際に税理士業を営んでいたのは1万7千人ほどで、そのほとんどが中小企業をシェアとしていた。日税連が社労士法との関連で会員税理士の社会保険関連事務取り扱いについて調査した記録があるが、それによると、全国で述べ83万件(年間)、税理士1人当たり平均134件も取り扱っていることが明らかになっている。
社労士法制定以前から税理士は、労働および社会保険諸法令に基づく事務手続きを、税理士業務に付随して行っているという既成事実を踏まえ、この既得権を認めてほしいというのがその言い分であった。
以上が労務管理士系の関連団体の法制以前の動きであった。