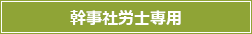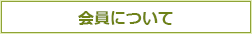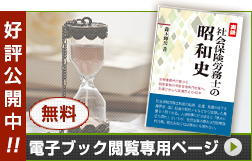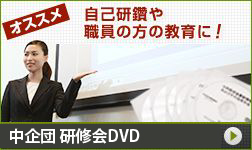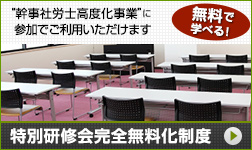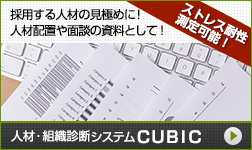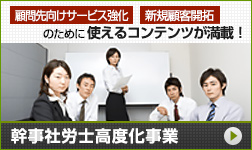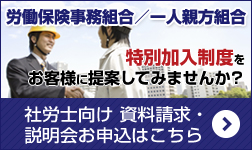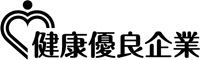トップページ ≫ サービス一覧 ≫ NETWORK INFORMATION CHUKIDAN ≫ 業種特化社労士の視点から
NETWORK INFORMATION CHUKIDAN
業種特化社労士の視点から(第51回 『運送業界(トラック)編』)
<石原 清美 氏>
この運送業界では「改善基準告示」という自動車運転者独自の時間管理を行い、正しい労働時間管理は必要であると言い続けています。そして、業務の始業終業時は必ず国家資格である運行管理者が点呼を行いますので、改善基準告示を理解するには運行管理者の資格取得も一つの方法だと思われます。
また、この業界は、厳しく困難な業種であると思われがちです。しかし、普段コンビニなどに商品があるのはドライバーによる配送のお陰です。人々の生活が成り立ち社会に貢献するやりがいのある必要不可欠な業種だからこそ、この素晴らしい業界に長年関与させていただいています。
そのおかげか、全国社会保険労務士会連合会より「働き方改革推進特別委員」の運送業担当として講演をする機会を与えていただきました。研修終了後には、受講者の方々より時間管理の方法、36協定の時間など様々な質問があり、また「苦手意識のある運送業でしたが、一度関与してみよう」という言葉もいただくなど、その関心の高さに驚きました。この講演については連合会HPでオンデマンド公開されます。重ねて全国の社労士会などで研修の機会があり、その度に、この業界には社労士の先生方が必要ですので、是非に関与していただけますようにとの願いを込めて講義を行っています。
●1.トラック運送業の現状
物流業界における自動車運転者の時間外労働の上限規制等が施行され、1年後には、960時間以内に厳守出来ているかの確認となりますので、おそらく、これからは行政指導が厳しくなります。
このような状況になると、限られた時間で、効率よく回数を稼げる方法など工夫を考えるドライバーも増えてきていますので、客先である荷主に頼るだけでなく、事業者自体が考えなければならない時代となっています。
●2.ドライバー不足に対する人材確保・採用対策
この業界での一番の問題点は人材不足で、若年者の応募が少なく、全体的に高年齢化しています。ドライバー採用、免許取得や賃金に対する待遇などについての問題も多く、それを解決できるような体制にしなければなりません。人一人を雇用するほどの求人広告費を支払っているところも珍しくなくなりました。
その対策として、居心地よく働ける労働環境でやりがいのある会社にすれば退職者がいなくなり、求人する必要がなくなります。このことから現在、勤務している従業員を今まで以上に大切にすることが重要となります。
こちら(9ページ記載)では、運送業の人材確保の求人方法など具体的な方法を紹介しておりますのでご参照ください。
●3.労働時間管理を運行記録計で行う方法
改善基準告示は告示ではありますが、法律と同じように考えなければならず、労働基準法と共に是正勧告の処分となる場合があります。ここで注意をしなければならないのは、この改善基準告示は自動車運転者にのみ適用され、運送会社の事務職員(運行管理者を含む)や倉庫作業員には適用されないことです。
また、一般的な時間管理と改善基準告示の内容の大きな違いは1日の始まりです。一般的な考え方の1日の始まりは夜中0時から24時間ですが、改善基準告示の場合の1日は始業時刻より24時間とカウントします。一般貨物運送事業では、運行記録計の装備が義務付けされており、デジタル式の場合はデジタコと言われ労働時間が記載されますのでそのまま計算することが可能です。他方、アナログ式の場合は、チャート紙に記入される針の動きで時間を確認しますので、それを拘束時間管理表などに転記しながらの計算が必要となります。
●4.正しい労働時間管理の必要性
最近では、法改正に伴いドライバーの労働時間を削減し、残業代を生活費としているドライバーの賃金低下を防ぐため、荷主に対して運賃値上げ申請を頑張って行っている運送会社と、ドライバーの賃金確保と売上維持のため、やむを得ずに法律を厳守しない運送会社とに二極化しているように思われます。
それゆえ毎日の長労働時間はドライバーの健康、賃金に影響があり、会社は時間管理の必要性に気付いているものの、その時間外労働上限時間を厳守せず、労働時間を大幅に違反していることがわかってはいますが、行政監査となるまで、管理を行わないと言い切るところも見受けられます。それは過重労働、賃金未払いなどの大きなリスクを抱えていますので、早急の改善、対応が必要です。
改善基準告示について、概要を表にまとめましたのでご参照ください。
●5.労働時間管理の対応についての成功事例
売上重視で、時間管理を全く行っていなかった運送会社が、時間管理の必要性に気づき研修を行いました。その具体的な内容はデジタコを利用して前月当月の分析を行い、翌月にはどのようにしなければならないのかを管理者自ら考える方式でした。研修が進む中、管理者と同時にドライバーの意識も変わってきました。最終的には、部署全体で1時間あたりいくら稼いでいるかなど、生産性の向上と利益の両立をめざすことができるようになり、またドライバー自身が自らの生産性の計算を行い、それが評価に繋がるという賃金体系を構築しました。ちなみにその事例をトラック協会で講演したことが、執筆書籍を出版する機会につながりました。
社労士業は、人に関する業務で、どのような立場であっても、最終的には人と人とのつながりであると思います。運送業での法律等を守れないと言われる事業者も多い中、前向きな考え方で真剣に取り組み、守っている事業者もいます。なにごとも、できないと諦めればそこで終わってしまいます。
運送業者は人々の生活を支えています。物流としては様々な運搬方法がありますが、最終的にはトラックで運ぶことが必要となります。そのために、トラック運送業がより良い業界になることで、人々の生活がより豊かになるのです。
 本稿執筆の石原清美先生による成功事例を記載した書籍
本稿執筆の石原清美先生による成功事例を記載した書籍
「中小企業のためのトラック運送業の時間外労働削減の実務・補訂版第3版」
(第一法規)(2024年3月10日発行)も併せてご覧ください!